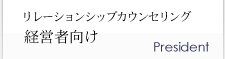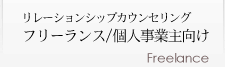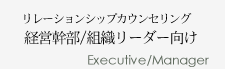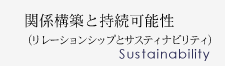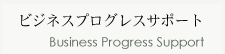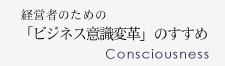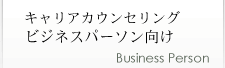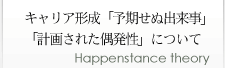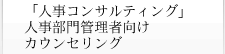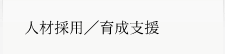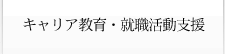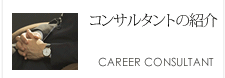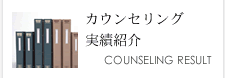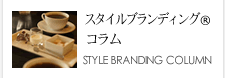- TOPPAGE
- スタイルブランディング®コラム
突然の構造変化が続く
意味ある知識の内容と性格が不断に変化していくがゆえに、 世界経済そのものが、突然の構造変化を続けていく。 当然、企業とマネジメントのあり方も、急速に変化していく。 ~P.Fドラッカー「P.Fドラッガー経営論集」 引用:「変革の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ================================================== 最近は、予測不可能な「突然の構造変化」が多くおきていると思います。 ドラッガーに言わせれば、予測できた範囲なのかもしれませんが・・ とい..続きを読む
今日の当然が明日の不条理となる
組織は、絶えざる変化を求めて組織されなければならない。 組織の機能とは、知識を適用することである。 道具や製品やプロセスに対し、仕事の設計に対し、 あるいは知識そのものに対し、知識を適用することである。 そして知識の特質は、急速に変化し、今日の当然が明日の不条理になるところである。 ~P.Fドラッカー「未来への決断」 引用:「変革の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 「組織に絶え..続きを読む
変革の時代
すでに一つのことが確実である。 根本的な変化が続く時代に入ったということである。 ~P.Fドラッカー「明日を支配するもの」 引用:「変革の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ================================================== 今までは、「仕事」「経営」という観点から、 「生き方」「キャリア」「マネジメント」についての ドラッガーの言葉を、多くご紹介してきました。 今回からは、「変革」という観点からのドラッガーの言葉をご紹介していきます。 ドラッ..続きを読む
リーダーについての唯一の定義
信頼がない限り従う者はいない。 そもそもリーダーについての唯一の定義が、 つき従う者がいることである。 ~P.Fドラッカー「未来企業」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 信頼・・というと難しそうな話しになりますが、 要は周囲の人間を「その気」にさせられるような人が いるかどうか?ではないでしょうか。 「その気」になるということは、 つき従う者の側の眼力も..続きを読む
信頼とは真摯さへの確信
信頼するということは、リーダーを好きになることではない。 つねに同意できることでもない。 リーダーの言うことが真意であると確信をもてることである。 それは、真摯さという誠に古くさいものに対する確信である。 ~P.Fドラッカー「未来企業」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ ドラッガーがいう「真摯さ」とは、よく言われる「真摯な態度」とも ちょっと違うような感じがしま..続きを読む
プロフェッショナルの条件
厳しいプロは、高い目標を掲げ、それを実現することを求める。 誰が正しいかではなく、何が正しいかを考える。 頭のよさではなく、真摯さを大切にする。 つまるところ、この真摯さなる資質に欠ける者は、 いかに人好きで、人助けがうまく、人づきあいがよく、 有能で頭がよくとも、組織にとって危険であり、 上司および紳士として不適格である。 ~P.Fドラッカー「現代の経営」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================..続きを読む
自らと部下に厳しく
成功している組織には、 愛想が悪く、あえて人を助けようとせず、 人づきあいもよくない上司が必ずいる。 冷たく、厳しく、不愉快そうでありながら、誰よりも多くの 人たちを育成する人がいる。 最も好かれている人よりも尊敬を得ている人がいる。 自らと部下に厳しく、プロの能力を要求する人がいる。 ~P.Fドラッカー「現代の経営」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ================================================ 4人のタイプの人たちが紹介さ..続きを読む
部下ができることを問う
強みを生かすということは、成果を要求することである。 何ができるかを最初に問わなければ、貢献してもらえるものよりも はるかに低い水準で我慢せざるをえない。 成果をあげることを初めから免除することになる。 ~P.Fドラッカー「経営者の条件」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 上司が考えている以上に、メンバーは自分の強みや得意なことを 発揮したい願望を持っているもの..続きを読む
部下の強みを生かす責任
部下の弱みに目を向けることは、間違っているばかりか無責任である。 上司たる者は、組織に対して、部下一人ひとりの強みを 可能な限り生かす責任がある。 部下に対して、彼らの強みを最大限に生かす責任がある。 ~P.Fドラッカー「経営者の条件」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 強みを生かす責任・・弱みに目を向けることは無責任・・ 私のような普通の人間には、 「そ..続きを読む
人材を育てる上司の原則
真に厳しい上司、すなわち一流の人間を作る上司は、 部下がよくできるはずのことから考え、 次にその部下が本当にそれを行なうことを要求する。 ~P.Fドラッカー「経営者の条件」 引用:「仕事の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 皆さんは、自分の部下に「要求」ができますか? 要求することは、こちらが「覚悟」することだと思います。 中途半端に何らかの要求をすると、 それは中途半端..続きを読む
![スタイルブランディング[STYLE BRANDING]](/img/common/logo.gif)