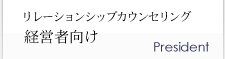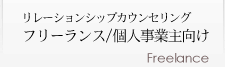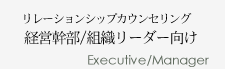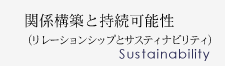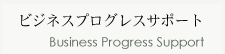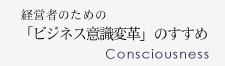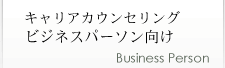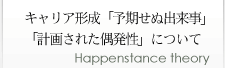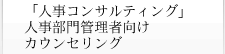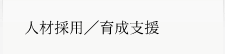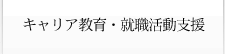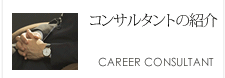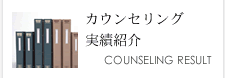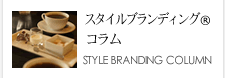- TOPPAGE
- スタイルブランディング®コラム
部下ではなく同僚として遇せよ
知識を基盤とする新産業の成否は、どこまで知識労働者を惹きつけ、 とどまらせ、やる気を起こさせるかにかかっている。 彼らの価値観を満足させ、社会的な地位を与え、社会的な力を与えることによって、 活躍してもらわなければならない。 そのためには、部下ではなく同僚として、高級の社員ではなくパートナーとして 遇さなければならない。 ~P.F.ドラッカー「ネクスト・ソサエティ」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ===============================================..続きを読む
人は費用ではなく資源
マネジメントのほとんどが、あらゆる資源のうち、人が最も活用されず 能力も開発されていないことを知っている。 だが現実には、人のマネジメントに関するアプローチのほとんどが、 人を資源としてではなく、問題、雑事、費用として扱っている。 ~P.F.ドラッカー「マネジメント」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ================================================= 難しいことを言っています。 要は、「人」をどのように捉えるかという、経営の観点から見た大..続きを読む
人のマネジメント
あらゆる組織が、人が宝という。 ところが、それを行動で示している組織はほとんどない。 ~P.F.ドラッカー「未来への決断」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 =================================================== 日頃、人的マネジメントに接している方や初めてマネジメントを行う必要となった 方のみならず、マネジメント能力というのは、自身のマネジメントやプロジェクト、 同僚、仕事そのものに必要とされます。 意外にも、毎日どこかでマネジメ..続きを読む
他社との比較で知る強みと弱み
他社はうまくできなかったが、わが社はさしたる苦労なしにできたものは 何かを問わなければならない。 同時に、他社はさしたる苦労なしにできたが、わが社はうまくできなかった ものは何かを問わなければならない。 ~P.F.ドラッカー「創造する経営者」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================== 確かに、この考えは重要です。 自分たちが得意とするところと不得手とするところを 客観的に比較掌握しておかなければい..続きを読む
強みの分析が教えるもの
強みの分析は、 既存の強みをいかなる分野で増強すべきかを教えるとともに、 新しい強みをいかなる分野で獲得すべきかを教える。 ~P.F.ドラッカー「未来への決断」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ これも「経過観測」が必要だということなのではないでしょうか? いずれにしても、マーケットからの目線です。 「強み」を見ていくのは、内側からの事情ではなく、 外側から..続きを読む
自社の強みを分析せよ
わが社が強みとするものは何か、 うまくやれるものは何か、 いかなる強みが競争力になっているか、 何にそれを使うかを問わなければならない。 ~P.F.ドラッカー「未来への決断」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ これは、「強みについて常に経過観測が必要である」と捉えました。 気がつかないうちに「強み」が競争力を発揮していない場合や、 「新しい競争力」を強みと認識で..続きを読む
強みは具体的で特殊なもの
あらゆる企業が自らの強みを知り、その上で戦略をたてる必要がある。 何をうまくやれるか。成果をあげている分野はどこか。 しかるにほとんどの企業が、あらゆる分野においてリーダーになれると考える。 だが、強みは常に具体的であって特殊である。 ~P.F.ドラッカー「乱気流時代の経営」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 今回のドラッカーの言葉は、 「強みは常に具体的であって..続きを読む
強みを機会にマッチさせよ
すでに起こっていることは何かとの問いに対する答えが、 企業や産業にとっての可能性を明らかにする。 この可能性を現実へと転化するには、 自らの強みを機会にマッチさせることが必要になる。 ~P.F.ドラッカー「未来への決断」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 「すでに起こっていることは何か」 「強みを機会にマッチさせる」の2点がポイントです。 世の中やマーケット..続きを読む
コア・コンピタンス
あらゆる者が、強みによって報酬を手にする。 弱みによってではない。 最初に問うべきは、我々の強みは何かである。 ~P.F.ドラッカー「乱気流時代の経営」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 ============================================================ 今回からは「コア・コンピタンス」についての言葉です。 コンピタンスという言葉は、ここ数年で一般的にもよく耳にするようになった言葉だと思います。 辞書を引けば、資産・資格・能力・..続きを読む
資源を割り当ててこその戦略計画
最善の戦略計画さえ、仕事として具体化しなければ、よき意図にすぎない。 成果は、組織のなかの主な人材を割り当てることによって決まる。 戦略計画は、将来において成果を生むべき活動に割り当てて、初めて意味をもつ。 さもなければ、約束と希望はあっても戦略計画は存在しない。 ~P.F.ドラッカー「マネジメント」 引用:「経営の哲学」著者:P.F.ドラッカー/編訳:上田惇生/発行:ダイヤモンド社 =================================================..続きを読む
![スタイルブランディング[STYLE BRANDING]](/img/common/logo.gif)